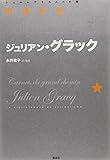本当に小さくて個人的な快挙
気がつけば2月も三分の一に差しかかろうというのにブログを更新していなかった。油断ならない。読むほうは遅々としているが少しずつ取り戻せてきたし、書くほうは順調でも不調でもない。とにかく普通。けれど、とにかく普通ほど安心できるものはないなとも思う。しかもここにきて体調と精神と、いい具合にバランスをとれてきているのだ。先般の山梨旅行がよかったのだろうな。
それでは描くほうはどうか。まあこれも普通。昨日も昼間に思いついたネタをメモしておいて、帰る途中にふつふつ煮詰め、帰ったら帰ったでなかなか思うようにならなくて苦戦しつつ、挙句の果てに煮こぼれしそうになるも、まあなんとか相応の最低限のかたちにしてツイッターにアップできたという次第だった。ありがたいことに私のような中途半端な創作しかできない人間の作品にも反応があり、昨日のものは私にしては珍しいくらいの評価をいただけた。
たくさんリツイートやいいねをしていただけることは当然のこと嬉しくあるのだが、そもそもたとえひとつだけでも、どんな方にしてもらったとしても、それは本当にありがたく喜ばしいことだと思っている。もちろんフォロワーの多い方にリツイートをしてもらったり、私には及びもつかないほどのレベルの方からなぜかいいねをもらったりすると興奮してしまうこともあるが、これは「ナンデ!?」という驚きのほうが大きい。いずれにせよ個人的にはどんな場合でも、リツイートひとつ、いいねひとつ、それぞれ平等だということには変わらないと考えるものである。
ただ、ただ、昨日の絵においてはそこに例外を作らざるをえない。
実はリスくんさんからいいねをもらえたのである。感動でときめいてしまった。いまさら言うまでもなくリスくん氏が私からしたら天上人であることは自明で、ガルパンの同人世界で大きな足跡を残してきた人であるからして当然なのだが、実はここには一方的な思い出がある。
私がガルパンにハマって最初に買った同人誌は氏の西ダジ本だった。劇場版からガルパンに入り、特にいいなと思ったのがダージリン(というか聖グロのみんな)と西さんで、その2人がいい感じに仲良くしてる豊かな発想がたまらなった。以前いたカイワイでやらかしてトラウマを負った私はまだあれこれ妄想を広げることにかなりの躊躇があったけれど、この本のおかげでその楽しさを思い出せた節がある。リスくんさんは私の想像力の恩人なのである。直接の因果ではないが、創作を続けられたのも、ドピコながら同人サークルみたいなこともできるようになったのも、根っこの経験にはあの西ダジ本があるのではないかと思う。
本当に正直を申すと、あまりに強烈すぎる作風からすべてのお仕事を追っているわけではなく、尊敬ゆえに遠ざけているところもある。そしてそもそも私の貧弱な発想と実力を考えれば、罷り間違おうとも接点が生じることはありえないだろうと思っていた。
しかし、どうしてか昨日の絵にいいねが付いていた。いい意味での評価をしてもらった(と見て差しつかえないよね……?)というのだ。「ウッッッソ、マジでリスくんがワイの絵を認識したんかッ!!!!??? なんで????」みたいな感じで眠気がみんな吹っ飛んでしまったけれど、そのあと冷静になりきって、思い出をほんのり回顧し、今度は感動がじわじわと湧きあがってきた。本当は全身を動かしたかったけれど、近隣の迷惑にならないように、私は心の中で歓喜の小躍りをした。
ガルパンにハマり、それからなぜか創作までするようになり、2年ちょっと。まさかこんなことが起こるとは思っていなかった。もちろんいいねをもらえたということは、どれほどすごい人からもらえたのだとしても、ひとつのいいね、ひとつの出来事でしかない。むろん接点ができたというわけではない。私の実力が向上したことの直接的な証明にはならない。ただ、やっぱりいいなとか、創作って楽しいなとか、そう思えた。私はまたユカイに酔い、ステキに勘違いし、またしばらく詩的に思い上がるための機会を得た。そういうことでしかなかった。それは世間的に見れば小さいことかもしれないが、存分に私のためになることであった。

あの道を往く
本がぜんぜん進まない。幸い創作で書くほうは乗ってきた感があるが全般的に読めなくなっている今日このごろ。どうしてなのかわからない。なにか得られるという手応えを感じられなかったり、単純に読むのが疲れるから面倒だったり、そのへんだろうか。描くにしても書くにしても、そういうときはある。
そこで無理をすることはない。対処法がわかっているならともかく、闇雲に動こうとすればさらなる苦悩を誘発するだけだ。スランプというのは自分の精神感覚と身体感覚の把握に対する無配慮からくると思う。ましてや私はなにかのプロではないわけで、できねーときはやらねーを地でゆきたいのだ。読めねえなら書訪も迷談もできねえ。
だからといってそれではここに書くことがなくなってしまう。そして怠慢なら怠慢なりにできることがありそうだ。対処というほどでもないが、自分の思う本を読むということが「最初から最後まで読みきる」ことを表している場合、そうする必要がない抜け道を探せばいいのである。このときにうってつけなのが詩集、名言集、辞書や事典(なにかテーマに特化した手軽なタイプがよい)、断章集といった本、つまり「どこから開いても大丈夫な本」だろう。この種の書籍は旅のおともにも適している。
で、本棚を眺めてみると、けっこうそういうのは並んでいる(自分の趣向が反映されているはずなので当然)。詩集は揃っているがその気分ではないなあ、と思ったところで目に入ったのがジュリアン・グラック『街道手帖』だった。この人は十年ちょっと前まで生きていたフランスの作家で、そのうちまとめて読みたいと思って作品をちまちま買い集めていたのであるが、本書は彼の実質最後の著作となった断章集である。これをテキトーに開いて、ぱらぱらとめくってみる。そしてこんな節が見つかるーー少々長いがまるまる引用しよう。
年をとるごとに少しずつ課されてきているささやかな禁欲、つまり煙草やアルコールや過食の自粛などは、当節流行りのあまり品のない表現で言うところの「創造性」に影響を及ぼさずにはおかない。土から上がってきて循環する樹液がいささか過剰であったり、生理学的な交換がより豊かになされたりすることは、芸術家の最良の生産性の条件のひとつなのだ。また資質[原文傍点]と呼ばれるものは、芸術家においては単なる感受性や想像力や性格の問題ではない。高い生産性を誇る芸術の主導者なら誰でもーーたとえその人が取りこんで消費するものが、ときに特定が困難だったりデリケートだったりするものだとしてもーー、これは信じて欲しいのだが、どこかに大食漢[原文傍点]を隠しているものなのだ。(p.246-247)
な、なんてことだ。いろいろ読み方は可能だが、なんとなくさぼってんじゃねーぞと言われている気がする。べ、べつに俺ァ芸術家じゃねーし生産力はもともと低い初心者だから練習しているんであってヨォ......ということなのだけど。それにしても作家なら酒も煙草も禁欲しすぎるなというのを97まで生きた人が言うのだからおっかない(この本を出した時点でも80を越えてるし)。自分も着実に加齢してきたけれど、冷静にこんな言辞を繰り出せるようになれるとはまったく思えん。
それはともかく、たしかに私はなにか道の者ではないが、なんとなくわからないでもない。この断章の特に後半部分では、高次な創作的生産性の背景には大量摂取があるとしているが、いくら自分がそういう生産力を求めていないところでも、それはそれで純然たる事実に違いないのである。この話は多くの分野で当てはまる。
私の恩師のひとりが卒論指導の際に毎回(そしておそらく毎年)しつこく言っていたのが大意として「質は量からしか生まれない」ということだった。優れた卒業論文を書くためには大量の文献にあたらないといけない。どうやっても余計な知識ばかり手に入るが、それをまとめて、肉を削ぎ落とし、さらに贅肉を削ぎ落として、ようやく本物ができあがる。まあ基本的な情報を書くだけならば概説書なりなんなり数冊でもあればできるかもしれない。しかしやはり1冊読んだだけでは書けないこと、10冊読まなければ書けないこと、100冊読んでやっと書けることというのが、そうしているうちに自ずと浮かびあがってくるのである。執筆物中にそんな文章がひとつあるだけでも、その全体の完成度は根本から一変するのだ。
量が質を保証するとは限らないが、たいてい質は量により裏づけられる。質の高いものを目指すと言いながら怠けて面倒くさがって最低限で済ませたがると、仮にそれなりに書けたとしても、見るからに文面がいっぱいいっぱいで余裕がないし、それでいて見かけでは文字が詰まっているのにどこか空虚であるようにしか受け取られなくなってしまう。だから私の卒論はそういうものになったのだ。楽をしようとすると廻り道に入り迷ってしまうという好例だ……いまでも迷ったままの気がしないでもない。
さて、話を戻すが、グラックによればこの件は芸術家に関してであった。力ある表現者はどこか「大食漢」であるという。ここで思い出されるのがよく聞くインプットとアウトプットの関係だ。しばしばこのバランスが大事だなどと見かける。私も同感である。だが実際のところアウトプットの量に対して膨大なインプットが必要であり、ある意味アンバランスな様相というのがその正体ではなかろうか。あるいはこの不均衡を立派に確立して初めて本当のバランスと言えるのかもしれない。当然ながら、どちらにせよ質を伴うたくさんの創作をしたいならば相当多数のものに触れ、ひいては吸収しなければならない。私はこの時点でもう遅れている。イベントで本を出すのも年一が限界。それも完成しなかったわけだから正しくは1年で0.8冊くらいしか書けていない。
とまれここでグラックの言うところの肝は、まずそれなりの奢侈を許して楽しむための精神的余裕が必要なことであろう。ここでお決まりの乱暴な解釈を押し進めてみると、この「大食漢」がただ大量に食べるだけでなく「美食家」の面も有しているところがあるように読めてくる。「芸術家」という語彙の選択からは、たとえば《私は文章を書いているから良い文章を書くために文章を読みます》といった泥縄的な道筋の付け方に限定させまいとする、ある程度まで広く視野を持とうとする意図を感じた。もっと態度とか感性とか、あるいはライフスタイルとか、そういう話まで根を伸ばしているように思う。煙草やアルコールに親しめば想像力が活性化すると言っているのでは決してないわけで、いろいろ暮らしや食、趣味など自分の楽しみのなかで自分に合った一定のこだわりを持つよう説いている気がしてならない。
......というふうに、たったひとつの断章でもこの程度までなら話を広げることが可能である。ただ問題として私がその本質を見据えているとはとても言いがたく、結局は独りよがりな着地をしてしまって、参照先をぜんぜん尊重できていないところであるな。まあ私は読んだ気になれたし楽しかったからよかったのだが。よかねえか。こんなことをしていたら卒論の二の舞さ。
ともかくも、本を読めないとき気軽に手を伸ばせる「どこから開いても大丈夫な本」をひとつでも蔵しておくのがオススメということだ。
最後に再三と重ねるようだが、私はプロの芸術家ではないし目指してもいないから、そこまで大食いにもグルメにもならなくてもいいはずだ。が、それでも自分で創作をするからには可能な限り納得いくレベルのものを作りたいよなあ、とも少なからず思う。できて当然とは思わないのでジレンマになるほどではないけれど、向上心が皆無というのも生きにくい。
幸いなことに世のなかはよりよいものを作るための方法やコツに溢れていて、目的や行き先の水準に応じて歩調を整えることができるようになっている。優しい人も多い。それこそ申し訳なくなるくらいに。これは本当に本当にありがたいことだ。ただ私自身そんな世界のぬくもりに触れつつも、そこから浮わついたり沈滞したりして、隠れるように、外れ調子のマイペースで進んでいるような自覚がどうしても心に残るのだった。
書訪迷談(12):どこか寂れた風景のなかに
突然の話になるが私の頭のなかには「はよ日本語版DVD(BD)出してくれリスト」みたいなものが設定されている。VHSでは発売されているのにそれきりになっていたり、あるいはそもそも媒体として出てすらいなかったり、そういう海外の作品が世の中けっこうあるのだ。ときおり祈りが通じてか発売された映画もないこともないが、たいていその気配すらなく、にわか映画ファンとしてはなかなか悩ましい。
たとえばアンソニー・クイン生涯唯一の監督作『大海賊』のBlu-rayを勢いあまって国外から取り寄せてしまったことなどもあるが、十分な語学力が備わっているわけでもなし、どう考えたって日本語で欲しい。加えてとりわけ熱望しているのは『サンタ・ビットリアの秘密』という愉快な佳作なのだが、Y○utubeなどで全編通して観れるもぜんぜん聞き取れないし(視覚的には楽しい)、もちろんそのうち出てくれるだろうなどと楽観はできるはずもない。まあこの手の作品が媒体になるときはたいてい脈絡がなく急である。まるでペリト・モレノ氷河の水の強大な圧力からくる氷河の崩落のように。そのたびにわれわれは飛びあがるほどたまげさせられるのだが、生き抜くコツとしては絶対に期待しないことである。こんな絶望を前提とした生き方、断じてオススメできない。あはは。
で、なぜこんな話題から導入してきたかという話だが、実はもうひとつ私が強烈にDVD化を願っている作品がある。その名も『フィオナの海』。VHSはまともに手に入らないし、そもそも再生環境がないし仮に入手したところでどうあがこうが観れない。数年前よく似た題材を用いた『ソング・オブ・ザ・シー』という素晴らしいアイルランド産長編アニメ映画が本邦公開で話題になったとき、この流れでソフト化ワンチャンないかと思ったけど見事にないままだった。もともとがインディペンデントだし、当時の日本での公開も岩◯ホールだったらしいから、規模的に考えれば順当なのかもしれない。だけどそれにしたってねえ。あらすじからしてすごく気になるのだけど、どうにか触れる方法はないものか。
要するに解決策として今回はそういう映画の原作を読んだということなのだ。
映画ではアイルランドが舞台になりロケがおこなわれたらしいが、原作ではスコットランドである。かの地に伝わるセルキーの説話を基にして作られたファンタジーの薫香に溢れる物語だが、こうして見るとヨーロッパ、ことに愛蘭や蘇格蘭においてケルト的命脈というものが根強い下地になっていることが実感される。栩木伸明『アイルランド紀行』の帯に「世界で言葉が最も濃い地」というフレーズが添えられていたのがいまだに印象的だけど、言葉にしても、途絶えることのない多様に湧いてくる想像力にしても、ケルト世界のそうした伝説と伝承の背景なしには考えられない気がする。気がするだけで、気のせいかもしれないけれど。
いやそうだけど、豊かな自然のなかに荒涼とした風が吹きすさび、でもそんな寂れた風景のなかに人々の感情に響いてくるものが目立たずに隠れていて、ここぞというときに「らしきもの」が発揮されてくる。こういうところってフィオナ・マクラウドやジョージ・マクドナルド、あるいはイェイツやジョイス、またあるいはジョン・フォードの映画にさえあったような気がしないかなあ。気がするだけで、やはり気のせいかもしれないだけどね。妄言よ妄言。私はこう感じましたという妄想の証言。
ともかく、あと個人的に『フィオナの海』の幻想的な側面は最低限のなかの十分であり、全体として折々にしっかり個々の人柄や人間模様が見受けられるのが好印象だった。落ち着いた雰囲気に包まれつつテンポのよい展開で読みやすく、映画版を参考して描かれた挿絵も作風と訳文に適っていて実によいものだった。少年少女だけでなく、大人になってから読んでもまだまだ面白い童話じゃないかと感じられる。それぞれタイプや方向性の違いはあれどもルイス・キャロルやローズマリー・サトクリフたちと同じように、この作者フライもそんな物語を紡ぎ、そしてわれわれの世界に残してくれたのだ。
それと作中で特に印象深い登場人物、いや登場動物といえばあざらしである。なかでも族の長チーフ・タンのどこか人間臭いところがたまらなくかわいい。フライはかなりの動物好きだったらしくその種の作品をたくさん書いているようだが(なぜか全然訳されていない)、そうした強みがケルトの幻想的な伝承と結びついた好例として本作が完成したと言える。もちろんあざらし妖精のセルキーはたしかにただの伝説かもしれないが、フィオナが弟を想い続けたことがたとえ紙上の文字としてあるいはスクリーン上の映像表現として表現されたにすぎないものであるにしても、人が誰かを想う気持ちというのは嘘にはならない。現実にファンタジーは存在しないかもしれないが、現実を生きるのに必要なファンタジーはあると思われる。ファンタジーは現実を生きやすくしてくれるから。
映画版のトレイラー↓
中央線が気絶してるあいだに
いそいそ帰ろうとしたのに見合わせてるもんだから迂回するついでの勢いで秋葉原に寄ってメロンで買い物をしたというだけの話である。おさとうさんの本を買った。あとmy cousinの本も。いずれもたいへんよき品であった。あと書いてて気づいたけど両方とも越後産じゃないか。まあそれはともかくよいものが買えたのだワ。

書訪迷談(11):物語は圧倒的に

- 作者: レスリー・M.シルコウ,Leslie Marmon Silko,荒このみ
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1998/01
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 17回
- この商品を含むブログを見る
「物語」という言葉もいろいろ定義があると思われるけれど結局よくわからないし、わからないままでもよいのではないか。私も自分の読書にそれほど明確な目的を持たせていないが「たくさんのものに触れ、ないような脳でも可能な限り多くを知り、結果的に多くを肯定できるようになれれば」くらいには漠然と思わないでもないので、やはりなにかいろいろわかっていたらもっと面白いのだろう。けれどこの出口のなさそうな難問に取りかかる余裕はない。
いやでもたしかに物語はどこにあるのかなど疑問を浮かべてみるのは楽しそうだ。たとえば人間は単に平面上を移動する図形にさえ順序立ったストーリーを見いだせるし、ただの図形であってもその種類が増えるだけで人間関係や性格の違いなど多様な意味づけできてしまうほどになるわけで、おそらく認知や直感のレベルで物語を好んでいると言える。ある対談の折に新城カズマがぽろっと「物語って認識の一形式なんじゃないか」なんてこぼした記憶があるのだけど、実際のところ研究の分野などで厳密にどう論じられているかは知らないが、私はこの人間主体の考え方はけっこう好きだ。読書中にそれを体験しているのは自分だ、みたいなことは以前の記事でも書いたかもしれない。反面、物語は本とかDVDのような媒体のなかにも「ある」気がする。いや、「いる」でしょ明らかにそこに。その気配を感じる。いったい物語とは?
……てほら、もう迷宮入り間近でしょ。いくら自分が認識の主体であるにしても対象がなければならないし、物語を発見しようとする力が意識か無意識かで働くにかかわらず、その構成要素のようなものがなければ片手落ちだ。どちらかにだけ属するとは言いがたい。そして物語はこうした関係を前提に存在していると表現することもできるかもしれないが、独立した中間的存在という感じもぜんぜんしない。関係そのものかというとそれもちょっと腑に落ちない。要するにわからん。
はい、この話やめ。前置きが重すぎる。はっきりわかる事実といえば、図形を介してであれ文字を介してであれ、われわれがたしかに物語を感じていることくらいである。楽しむのには差しあたりそれで十分ではなかろうか。
新年最初の(きちんとした)読書はレスリー・マーモン・シルコウ『儀式』となった。文庫収納ケースを整理中いくつか見比べていて目に入るや「そういえば持ってるのに読んでなかったな」と手にとって読みはじめた次第である。当然のこと予備知識は皆無。邦訳は本書ともうひとつあるが同じ作品らしく、しかも同じ訳者によって新しく訳しなおされたもので実は単純な文庫化ではないようだが、いずれにせよ既訳は本作のみ。そして現在はいずれも絶版。そんな事情なせいか作者の名も日本ではあまり知られておらず(日本語のWikiがない)、もれなく私もそのうちのひとりだった。
だが読み進めてみて驚いた。これはかなりすごい本だ。なぜならそこには物語があったから。さっきわからないという話をしていたくせに、これは物語だと感じるのである。こんなことがあるのだ。
この小説はまず詩文で幕を開ける。基本的な形式は散文だが、作中にたびたびインディアンの口承文芸が差し挟まれていて、ありきたりではないただならぬ雰囲気を初端からまとわせている。話の主筋をざっくり説明すると、戦争後遺症で精神を傷めたインディアンの青年が部族の儀式を通じて自分を取り戻すというものである。しかしここにさらに多くの問題が絡みつく。混血であることの宿命、伯父への憧憬、白人に対する視線……戦争、人種と差別、家族や友人や女性との関係……あまりにも切実な重荷が山積している。さらに主人公テイヨの精神状態さながらに、本作のとりわけ前半部では時も場面もたびたび移り変わることから、読者は状況が複雑かつ深刻であるのだと否が応でも把握する。私もわりと戸惑った。
たださすがというべきか、ある種の錯綜した構成を持ちながらも明快で丁寧な文体がしっかり道筋をつけて導いてくれる。そのおかげで私もなんとか迷わずに歩ききることができた。正直を申せば読むこと自体にはかなり苦労したけれど、著者がすぐれた書き手=語り手であることは微塵も疑がいえなかった。おそらく「物語り(ストーリーテリング)」に相当なこだわりや並々ならぬ愛着があるのではないかと読みながら推察していたのだが、親族からの教えに大きな影響を受けていたと訳者の解説にもあるとおり、やはり身近に物語のある環境に育っていたのだそうだ。語りというおこないが聞き手の存在を抜きにしてはできないことを身体で覚えているわけである(めえぜるさんがどうあがいても考慮できないところなので羨ましい)。それゆえ面倒事を多分に扱うにもかかわらず、ずっと寄り添われているような安心感があった。
そしてこうした下地があるおかげなのだろう。戦地で日本兵を殺さなければならなくなったり、人間関係における不和や人種的な差別に直面したり......読みながらこちらも不穏にそわそわとしてしまいそうな、ともすればイデオロギッシュな告発に堕しかねない要素に向き合いながら、切実ではあるがあくまで冷静にこの小説は書かれているように思われた。もちろんまったくないわけでもなく、特にネイティヴ・アメリカンの土地を侵して奪った白人とキリスト教に対する怒りが克明に描写される。先住民たちが辿らざるをえなかった困難の歴史に関して作者は間違いなく意識的だ。そして並々ならぬ思いがあった。だからこそこの作品が著されたのではなかろうか。新たな時代にふさわしい、新たな時代の人々に伝えるべき物語として。
作中で儀式を執りおこなう老メディシン・マンの言葉からもどことなくそんな姿勢が、決して楽観ではないが思いのほか前向きな態度が、どこか垣間見えた気がする。新しい時代、新しい世界においては新しい儀式が求められる。伝統は少しずつ新しくなる。
「儀式はこんなふうにいつも変化しておるのじゃよ」
蛇足で妄言のようなことを垂らしてしまうと、読後感はフランツ・ファノンよりかは保苅実のときのほうに近かったな、なんてふと思った。白人へのコンプレックスのくだりなどはたしかに『黒い皮膚・白い仮面』がうっすらちらつかないでもないが、それにもまして、歴史と深く結びついた部族の物語を肯定するという点から見れば『ラディカル・オーラル・ヒストリー』を思い出さずにはいられない。いずれの本にしても私はよい読者でもなかったし印象論で単純比較をすべきではないのは承知だが、私としては保苅やシルコウを読むほうが性に合う感がある(ファノンの立場を悪く言うつもりは毛頭ない)。
というか話が逸れそうだが、あまり前のめりに構えなくても『儀式』は無理なく読める傑作だ。人間も動物も植物も、そして人間の作ったものも、ありのままに描写してゆく筆の力がある。この作品は、独りよがりな人間中心主義を脱しながらも人間存在に愛着を向けるヒューマニズムのにおいがする。私のような正義や道徳の問題を恐れる(そこから完全に無関係でいられることなどできないというのに!)弱い人間でさえも、目を背けずに踏破できる。それはやはり、聞き手たる他者の存在があることを前提として作者により追求(究)され紡ぎあげられた物語それ自体がきわめて圧倒的な存在だったからであろう。大小様々な問題を矮小化することなく、しかしそれらを超えて、覆いこんでいるのである。
それゆえの批判もありうるし、もちろんもっと当事者となる人たちが読めば異なる反応を示すかもしれないし、そもそも私が愚かしくも大いに誤読をしていることこそ請け合いなのだが、こうして文学作品に気圧される体験というのはなかなかないため貴重だった。多くの作品を読み慣れている方々からすればそうはならないのかもしれないが、少なくとも普段と雰囲気の違った読書ができるのではないかと思う。誰がここを覗くのか、それに誰がここにきて本を読みたくなるのか不明(ある意味では自明?)だが自信をもってオススメしたい。惜しいのは前述のとおり絶版で特に文庫版の中古価格が若干高騰していることである。図書館などで求められたし。
それと、この作品自体が見事な物語なのでその話をしてきたけれど、作中でも部族の物語が青年を心を救済しているのは非常に興味深かった。物語の秘める力、そしてそれゆえの危険性を感じずにはいられない。明確に覚えてないからいまやなんとでも言えてしまうけれど自分が小説を書こうとした動機も、逸見エリカの魂は救済されないといけないから物語が創られなければならないとか、実はそんなだったのではなかろか。いや知らんけど。
あと本当にもうひとつ思ったのは、書こう書こうと思って必死になってやっとこ落としこんだ自分の文章ほど(少なくとも書いてからしばらくは)ブサイクに感じられるものはないということだ。西脇順三郎は「詩を詩として書こうとすると詩から離れる」と、あとダリだったか誰だったかが「パンをパンとして描こうとすると煉瓦になる」と言っていた気がするのだが、要するにそれである。今回の記事は読んだ本のことを久しぶりに書こうとして、いまこの文章を書いているあいだにも気合の空回りでどんどん膨れあがっている。集中しようとすると逆に視野が狭まり、結果として浮いた文ができあがる恐怖も拭いきれない。それに相変わらず「語るほど失われるものがある」という気がするし……自分の怠慢で間が空いてしまったことを言い訳にしたくはないが、継続による地道な鍛錬と模索ほど信頼に足るものはないと再確認した。特に私のような凡人にとってそれが唯一の道なので、今年もちょっとずつ進んでゆきたい。頑張るぞ。